陸上自衛隊・10式戦車 Op.474
2019年12月12日
2つのカーモデルの乾燥待ちにもう一つ製作を開始します。次は陸上自衛隊の主力戦車、10式戦車です。10式戦車はその名前の通り2010年から配備が始まった陸上自衛隊の国産4代目にあたる主力戦車です。先代の90式では大きくなりすぎたため北海道以外の日本本土では使いづらくなっていました。運ぶのにも砲塔を外して車体と別々に運ばなければ奈良かかったり、橋も1/3くらいは通過できなかったりです。仮想敵国が北の大国だったころはそれでもよかったのですが、西の方の国々にも警戒が必要になったいまでは、北海道以外での作戦行動が不可避で、そのためサイズを小さくする必要がありました。そうして開発されたのが10式戦車で、重量級ばかりの諸外国の戦車に比べるとちょっと異質の存在になっています。高性能のまま小型軽量化するのは日本のお家芸ですからね。日本の戦車らしいですよね。
キットはアオシマの1/72です。1/72ですから掌に乗るほどの小ささですが、履帯は部分分割野組み立て式ですしエッチングパーツも入っている本格派です。72スケールはしばらく作ってなかったので老眼の私にはちょいと不安がありますが、パーツ数は少ないので2つの車の合間にサクッと作ろうと思います。
それではさっそく製作にはいります。つづきをどうぞ・・・
車体の組み立て
説明書では砲塔の組み立てから入るのですが、ここはいつもの手順で下から順番に作っていきます。理由はなにもないのですが、単なる習慣ですね。
サスペンションアームに派手なヒケが見られたのでパテで補修しました。またサスペンションアームは角度を三種類に変えて作る事が出来るのですが、ちょっと遊びというかガタが大きく、適当に作るとちゃんとまっすぐに並ばないので、なんども慎重に角度を合わせて全部の転輪が接地できるように注意しました。
車輪の組み立て
車輪を組み立てます。転輪は片側5個なのですが、誘導輪もまったく同じ形をしているので片側6個ずつ作ります。これをサスペンションに仮り組みしてちゃんと10個の転輪が残らず接地するか確認をしました。
実はガタがあるのは転輪のサスペンションアームだけじゃなく、誘導輪も同じです。誘導輪は実車では履帯のテンションを調整するために前後に振れるようになっているのですが、キットでは組み立て式履帯の長さに合わせて角度を決めてやる必要があります。ですから誘導輪のアームは接着しないで、履帯を取り付ける時に履帯と一緒に位置を決めて接着するのがいいでしょうね。そのことにアームをつけちゃってから気づいたので、接着剤が固まる前に剥がしておきました。あぶないあぶない・・・(;^ω^)
(全作品完成まで あと125)










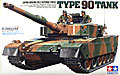

コメントを残す